| 洞穴名 |
不二洞(ふじどう) |
| 別 称 |
申の穴・庚申の穴・大福寿穴・福寿山の穴・不二穴、富士穴 |
| 所在地 |
群馬県多野郡上野村大字川和 川和自然公園内 |
| アプローチ |
秩父市街より国道299号を群馬方面へ進む。父母トンネルの手前を案内板に従い左折、突きあたりの自然公園案内所から徒歩7分の所に開口している。周辺図(マピオン地図)
|
| 管理状態 |
観光洞(上野村川和自然公園案内所℡0274-59-2146)
|
| 縦断面分類 |
竪横複合洞 |
| 規 模 |
総延長587m 高低差?m(もぐらケイビングクラブ〔1977〕:測量図より) |
| 洞穴情報 |
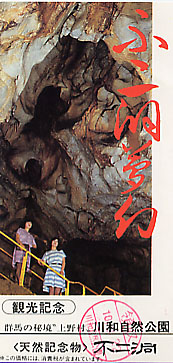 約1200年前(奈良時代から平安時代に移る頃)、野猿が一ヶ所に集まって騒いでいることから猟師が発見、「庚申の穴」「申の穴」「猿の穴」と呼ばれた。約800年前(鎌倉時代)には、大福寿山にあることから「大福寿穴(おふくじあな)」と呼ばれるようになり、約400年前(安土桃山時代)に川和地区にある藤原山吉祥寺の僧・中興開山上人が探検、修行洞として世に知らしめるようになった。江戸時代には、悦巌上人が日本に二つとない洞穴であるとして「不二穴」と改名した。 約1200年前(奈良時代から平安時代に移る頃)、野猿が一ヶ所に集まって騒いでいることから猟師が発見、「庚申の穴」「申の穴」「猿の穴」と呼ばれた。約800年前(鎌倉時代)には、大福寿山にあることから「大福寿穴(おふくじあな)」と呼ばれるようになり、約400年前(安土桃山時代)に川和地区にある藤原山吉祥寺の僧・中興開山上人が探検、修行洞として世に知らしめるようになった。江戸時代には、悦巌上人が日本に二つとない洞穴であるとして「不二穴」と改名した。
近代になってからは、1962(昭和37)年に地元の青年:高橋隆氏らが「空穴(からあな)」を探検、1965(昭和40)年には群馬県指定天然記念物となった。その後、上野村では観光資源として徐々に整備し、1969(昭和44)年に「空穴(からあな)」の螺旋階段が完成、そして次第に「不二洞」と呼ばれるようになった。1977(昭和52)年には東京のもぐらケイビングクラブによって測量が行われ、1988(昭和63)年に長さ120mの人工トンネルが完成(現在の入口)。1992(平成4)年には新洞部が発見され、そこから本州には生存しないとされてきたヒグマの骨化石が発見された。1998(平成10)年には第3セクター:株式会社上野振興公社による経営となり、2001(平成13)年に「空穴(そらあな)」まで観光部分を延長して現在に至る。
なお、村単位で全国地勢の様子を記した明治政府による官撰地誌「皇國地誌」には、「空穴(からあな)」について、「臨テ其下ヲ窺ヘハ漆然トシテ闇シテ測ルヘカラス、試ニ石ヲ以テ之ニ投スレハ石墜テ届ル所ヲ知ラス」と記載されている。
上野村振興公社によるこの観光洞は、秩父帯南帯乙父沢層のレンズ状石灰岩帯にできた鍾乳洞で、乙父地区にある「生犬穴」と共に群馬県の二大鍾乳洞として知られている。関東一の鍾乳洞と呼ばれ、上野村によるロープを使った計測結果は全長約2200m、もぐらケイビングクラブによる測量結果によれば総延長587mである。
入口は120mの人工トンネルとなっており、竪穴「空穴(からあな)」の底に連結している。ここには約30mの螺旋階段が設置されており、ここから竪穴を登ることになる。洞内には宗教的な名称が付けられており、風化が進んでいるが石柱など二次生成物も豊富である。2001年には観光部が延長され、ドーム竪穴「空穴(そらあな)」が追加された。現在も新洞部を調査中。
群馬県指定天然記念物。
入洞料金600円。(文責 千葉伸幸)
|
| 入洞者 |
千葉、雨宮、小塚、佐々木、赤木、細野、小園、千葉さ、山下、朝倉、宮野原、渡辺、村野て、酒井、中野、星野、本田、木嵜 |
| 最終入洞日 |
2023年5月3日(千葉の、千葉さ)
|
| み る |
スカイブリッジ:川和自然公園から延びる天空回廊。夜間はライトアップされ美しい。 |
| たべる |
道の駅うえの:国道299号沿い。勝山。イノブタ丼などが手頃な値段で食べられる。℡0274-20-7021 |
| いやす |
「ヴィラせせらぎ」:日帰り入浴可。国道299号沿い。℡0274-59-2585
|